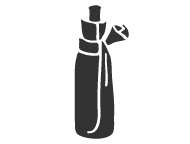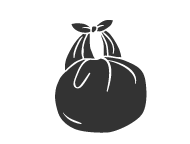��̤����ΤϤʤ� �� ��ˤ����� ��
��̤����ε����Ͻ��⤢��ޤ��������θ����ϸŤ������ɻ���Ȥ����졢�����Ϻ���ˤ����Ƥ����ȶ�Ȥ��ƻ��Ѥ���Ƥ����ȸ����Ƥ��ޤ������ͻ����������ʲ֤κ��ݤ�����ˤʤꡢ���ʤ���ʪ����ݤ˽Ф�ü�ڤ줫�顢����ɬ���ʤȤ��ƤΡּ�̤����פ����ޤ�ޤ�����

 ��Kenema�۱ﵯ���������
��Kenema�۱ﵯ���������
���ʤǽ��褿��̤����Ͼ��פǻȤ��䤹������̱������˹�����Ʃ���Ƥ����ޤ�����
��̤����γ����������������������Ǹ����������ϥ��Ȥ��Ƥ���������̵������������ۤ�������Ȥ���Ƭ����ä��ꡢ�۵��ˤ����������Ӥ䡢����ʪ�ν����˻Ȥä�����������ǽ����Ǥ�����
���Ӥ˱����ƹ��ߤ�Ĺ���ǻ��ѤǤ����ڤ�äѤʤ��Τ��η�����®�����ˤ�ͥ�졢�����̤Ǥ��������ޤ���������˼��ѥ���������Ǥ�̵�������ͤο�ʥե��å�����ƥ�Ȥ��ƤⰦ���졢������ä���̤����Υǥ�������礦�ּ꿡��碌�פȤ�����ɾ��Ⳬ����Ƥ������Ǥ���
��������ˤʤ�ȡ��������Ѥθ���ȶ��ˡ������פȸƤФ���ˡ�����ޤ����������쵤�˸��夷�ޤ�����
����ȶ��ˤ��Υǥ������¿�Ͳ������Ť����鰦������ŵŪ�����ͤ����Ǥʤ��������ʥǥ�����ˤ�äơ�����ƥꥢ��ե��å����ʤ����������ӤǤ�Ȥ���褦�ˤʤ�ޤ�����
�����ȤˤȤ���ʤ��ڤ��ߤ����ϡ�������Ѥ��ɤ⺣���Τ��Ѥ�뤳�ȤϤʤ��ΤǤ��礦��
�����ʼ�̤��� �� ���������å� ��
�����λͳѤ��ۤȤ��ʤɤ�ʤ��졢��̤����ϼ¤ϤȤäƤ�ͥ���ʤ�Ǥ��������Ƥ��η����ˤ⤭����Ȱ�̣������ޤ���
��̤������ڤ�äѤʤ�������ˤϤ�������ͳ������ޤ���
- �� �����䤹�����ݤ����ޤ�ˤ�����
- ��ʬ����ȯ���䤹���Τǡ�����Ū��
�̤�Ƥ⤵�äȥϥ��˳ݤ��Ƥ����Ф����˴����ޤ���

- �� �����Ƥ����Ф�ʤ�
- ������ȥե������������Ʊ���������ʤΤ˾���ȥ���ѥ��ȡ�
ι�Ԥ䡢�����ȥɥ������ݡ��ĥ�����ˤ��Ŭ��
- �� �����ʥ������˥��åȤǤ���
- ���Ӥ䥷����˱����ƻȤ��פ��������˥��åȤǤ��ޤ���
Ⱦʬ�˥��åȤ��ơ��ߥˤ����ܤ�ˤ⡣
- �� �Ȥ�����̵����
- ��̤����˥롼��Ϥ���ޤ���
�ȤäƤ��ɤ������äƤ��ɤ����ץ쥼��Ȥˤ⡪
��̤����λȤ���
- �� ��Ƥ�ڤ���
- ��100��μ�̤����ϡ����פ�Ĺ������
�����ƻȤ��ۤɤ˽��餫��ȩ��������Ǥ����ޤ���
�Ť��ʤä��餪�ݽ��Ѥˤ��Ƥ�����������⾲��Ԥ��Ԥ���������Ƥ���ޤ���

��̤����ΰ���� �� ����������ˡ ��
�錄�������ϡּ�̤������Ƥ�פȤ������ȤФ�Ȥ��ޤ�������ϼ�̤����ϻȤ��лȤ�����ۤɤˡ��ɤ�ɤ�Ȥ��ͤ�������Ǥ�������Ǥ���
��ǫ�˰������ƻȤ��Τ������ΤҤȤġ�
�����Τ褦���������������Ȥ��ݤ��Τ������ΤҤȤġ�
��̤�����ï�⤬���ڤ˻Ȥ����Ρ��ʤΤǡ���ޤä��롼��Ϥ���ޤ��Ǥ⤽������(����)���ΤäƤ����Ȥ���Ƥ䤹���ʤ�Ȼפ��ΤǤ���
- �� ������
- ��̤����Ͻ����������Ͽ�����ޤ�����ΤȤ�ʬ���Ƥ��������ޤ��礦��
����Ͽ����Ф䤹���Τǡ���������ä����������Ǥ���
��̤����϶���ľ�������ˤϼ夯����������Ƥ��ޤ��ΤǤʤ�٤��������ޤ��礦��
̤���Ѥ�Ĺ���Ȥ�ʤ����⡢���ٿ��̤��Ƥ��餷�ޤ��ޤ��礦���������뤳�Ȥǡ�Ĺ���ݴɤ����Ϥ�����Τ��ɤ��Ǥ���ޤ���

- �� ü�ΤۤĤ�
- ��̤����ϡ�ü���ڤ�äѤʤ��ˤʤäƤ��ޤ��������ˤϡ�������Ʊ���Ū�פȤ���������Ť������ۤʤ�ǤϤ���ͳ������ޤ���
�ǽ�Ϥ������λ��ˤۤĤ줿�夬�ФƤ��ޤ������Ϥ��ߤ�;ʬ�ʻ���ڤäƤ��ޤ��ޤ��礦������ˤۤĤ�ϼ��ޤꡢ�ե��������夤�Ƥ��ޤ��ΤǤ��¿�����������
 �ڻ����۲�����������
�ڻ����۲����������� ��Kenema�۲Ƥ���ʪ�����ۤ��Ǥ��绰��
��Kenema�۲Ƥ���ʪ�����ۤ��Ǥ��绰��
�Ȥ��лȤ��ۤɤˡ����ä���Ȥ��ʤ���������Ǥ����ޤ����ּ�̤�����ơפ�����ڤ���ǤߤƤ���������
��̤������Τ� �� ���������� ��
��̤����ˤ��礭��ʬ����2������������ˡ������ޤ���
�ҤȤĤ��������⤦�ҤȤĤ������Ȥ�����ˡ��
-
- �� ����
- �ǥ�������سԤ����餫���ˤ��ߡ��������äʥ���ǡ������̣�襤�Ȥʤ�ޤ����ޤ����ݤ��Τ�Τ�����Ƥ��뤿�ᡢȩ���꤬�褯��ͥ�������礤�ˤʤ�ޤ���
ɽ�Τʤ���������̥�ϤǤ���
�����ؤΤ������
 �ڻ�����Ϯ���롡�Ծ��η�
�ڻ�����Ϯ���롡�Ծ��η�
-
- �� ����
- �ǥ�������سԤ��Ϥä���Ȥ��Ƥ��ꡢ�٤��ʥǥ������ɽ���Ǥ��ޤ����ޤ�����ɽ��������˭�٤Ǥ���
�����Τ褦�ʤ��줤�ʥ���ǡ������ϤǤ��ޤ���
��������Ѥ�������������ǽ�ʤΤ����Ū����ʥ֥�Ǥ���
���ѻ��ߤΤۤȤ�ɤϤ�����μ�ˡ����������Ƥ��ޤ���
 �ڥߥ䥳��ۥ�ȥ������̤������Ϥ���������
�ڥߥ䥳��ۥ�ȥ������̤������Ϥ���������